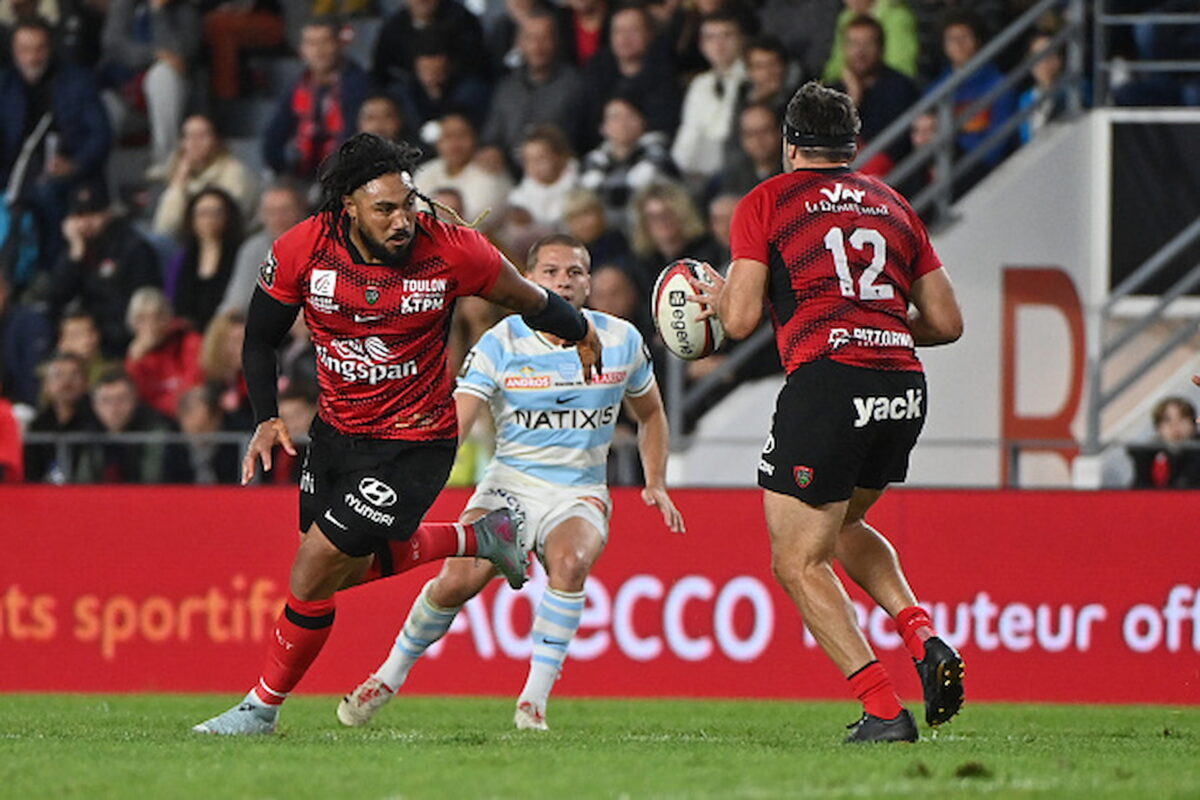うんと昔。NHKの土門正夫アナウンサーの名調子があった。
「攻めるメイジ。守るワセダ。ワセダはここからが強いんです」
国立競技場のゴール前。たくましい紫紺の力攻めを細身の赤黒がひざ下へのタックルでぎりぎり阻む。なんべんもなんべんも。数万の観客の叫びが重なって空気を揺らした。
2025年10月25日の同じスタジアム。
「攻めるオーストラリア。守るニッポン。ニッポンはここからが強いんです」
開始19分。オーストラリア代表ワラビーズは、ジャパン陣トライライン正面右5mのあたりでPを得た。7-0のリード。3点を欲しない。ワールドクラスの突破力を誇るプロップ、アンガス・ベルが、地面の球を足で触れたのちに抱え、あえて力をゆるめて当たる。
しっかり防御の整う最初のところでは無理をせず、2波、3波とたたみかければスコアできる。そんな算段だ。連続のぶちかましが始まった。
10フェイズ。腕を突き上げたのは桜のエンブレムの面々だった。ゴールドのジャージィのノットリリースで1分間の攻防は終わった。
身長201㎝のワーナー・ディアンズ主将が、195㎝のベン・ガンターが、やはり頼りになった生きる偶像、189㎝のリーチ マイケルが、みんな指の先を芝につけて、これ以上なく低く構え、義務ではなく権利のごとく突き刺さった。

母国と対峙のガンターは15-19の惜敗後、取材スペースで述べた。
「相手がラックのまわりを執拗に攻めてくることは予測できた。よいタックルはあったと思う。(ジャパンは)アタックのよいチームだからこそ自分はディフェンスで存在を示したかった」
188㎝の7番、下川甲嗣は19分19秒、168㎝の軽量フランカーさながら、地を這う素早さでトライをセーブ、下敷きから起きて、すぐ危険な側へ回り、同34秒にもういっぺんインゴールを守った。
試合後の会見。ワラビーズのジョー・シュミットHC(ヘッドコーチ)はジャパンの印象的な選手の名に「シモカワ」を挙げた。映像でこの場面を見返して、60歳の指導者は「目利き」だとわかった。
かつては「小柄=低さ」だった。ジャパンは体格に劣るので芝をタッチしなくてはならなかった。いま、ものすごく背の高いディアンズはちゃんと胸を地と平行にできる。「低い構え」を構成するのは物理の事情ではない。意識なのである。
1997年3月8日の個人的な体験を書きたい。全早稲田大学(現役に有力卒業生をまじえた編成)のアイルランド/イングランド遠征のコーチとして敵地でケンブリッジ大学とぶつかった。
46-62で負けた。トライ数は7対10。ここが問題なのだが反則数は23対8であった。
28年後のジャパンと同じようなディフェンスをことごとくオフサイドとされた。手をつき、倒し、動き、手をつき、また倒す。中盤や敵陣でも実行した。ラック最後尾の10㎝手前に指をおくことは徹底したつもりだった。
アフターマッチファンクションでレフェリーのジョーンズさん(あんまり悔しいので名前を覚えている)によれよれの英語で異を唱えた。
「わたしたちは絶対にオフサイドをしていません」
すると地域協会の公認である人物は明かした。
「芝に手をついて、あんな勢いで飛び出してくるなんて、いままで見たことがない」
次の試合は対ダーラム大学。こんどは62対34の快勝だった。主審のジョン・ピアソンさんは前年度のヴァーシティーマッチ(オックスフォード大学対ケンブリッジ大学の伝統の定期戦)を吹くなど国内トップ級であった。ペナルティーのカウントは12対9。終了後に話した。
「よーく見るとオフサイドではなかった」
時は流れ、現在では、南アフリカ代表スプリングボクスの巨人も短距離走者のスタートのように身をかがめる。1996年に実質解禁されたプロ化が浸透、どこのだれであれ、よく鍛えられ、スキルもより確かになって、そうでもしないと止まらないのだ。
大きな人間でも小(地を這うヒット)を選ぶのは、状況によってはスモールならではの利があるからだろう。
ひとつの例がジャパンの14番、石田吉平の「詰め」である。

前述の10フェイズを積んだのちのワラビーズの反則を誘ったのも、167㎝で75㎏のウイングの一撃であった。外へ散らされ、左タッチラインのきわにパスがつながると無人のピンチ。184㎝、92㎏のアンドリュー・ケラウェイとの距離を迷わずに詰めた。
キャップ46の15番、ケラウェイにすると、岩が迫れば視野に収まるが、小石が下半身めがけて高速のまま飛んでくるのでよけられない。転んで、からまれ、ジャパンのファンのてのひらを拍手で痛くさせた。
視界から消える。巧みなフットボール選手なら心がける。一般にはおとりのポジショニングや幻惑のランを用いる。石田吉平の場合はいつもの位置に立って、なお待ち伏せに等しい。外→内への複数の不意打ちタックルもうまく決まった。
10年前。170㎝・80㎏のサイズにしてウェールズ代表キャップ87のウイング、シェーン・ウィリアムズがこう語るのを聞いた。
「大きな人間が小さな人間をタックルするよりも小さな人間がビッグなタックルをするほうが本当は楽なのです。もちろん、そのためには自分のパワー、スピードを鍛えなくてはなりません」
ジャパンはもはや2m超のタワーをキャプテンに抱く。それでもなお「極度の低さと速さ=強さ」を追い求めなくてはならない。実利(そうしたほうが勝てる)を文化(そういうふうに生きてきた)がくるめば、そこに大勝利は待っている。