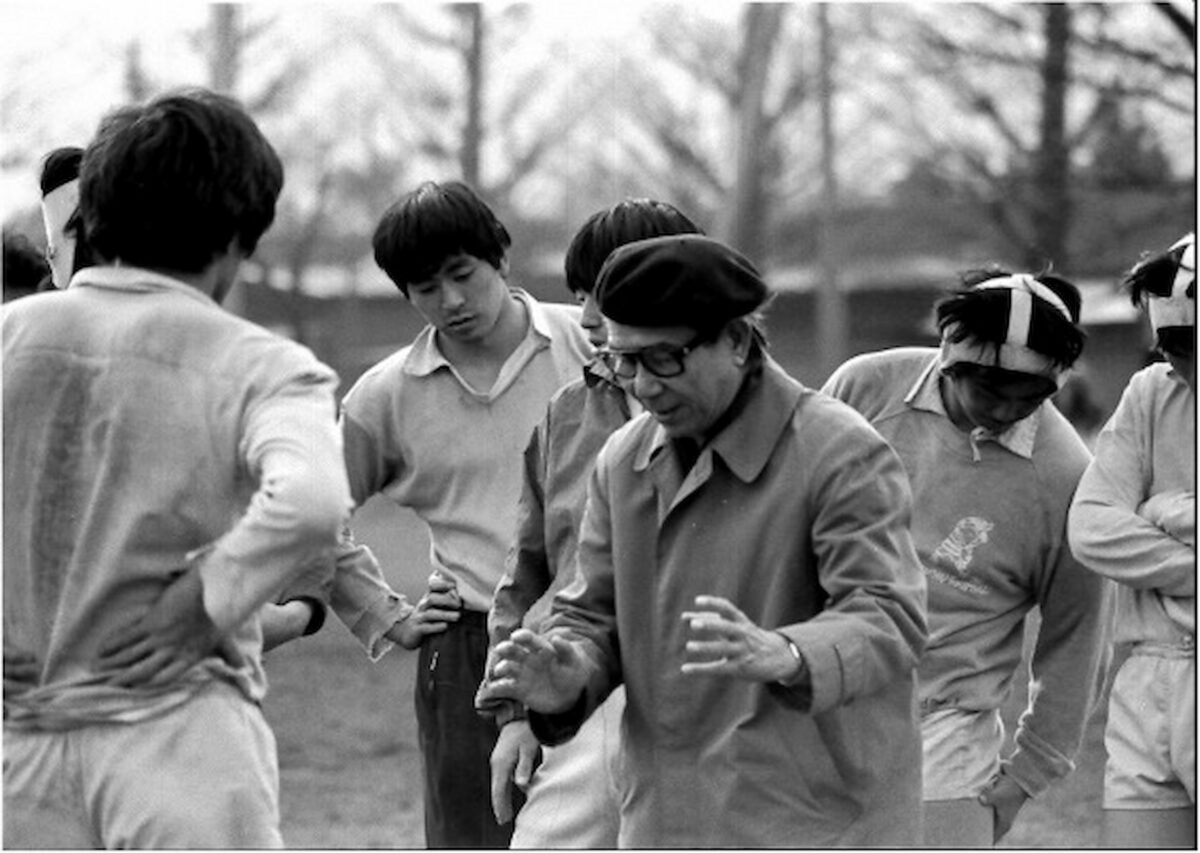今回のNZ遠征でフランスはとうとう勝利を掴むことができなかった(7月5、12、19日と3テストマッチ)。ファビアン・ガルチエ体制になってから3連敗は初めてのことだ。これでNZとの戦績は彼の体制下では3勝3敗となった。
シックスネーションズで優勝した主力選手不在のグループでNZに乗り込んだ。この地でフランスが勝利を挙げたのは2009年に遡る(27-22)。ティエリー・デュソトワール、パスカル・パペ、フランソワ・トランデュック、ヴァンサン・クレール、マキシム・メダール、そして現在フランス代表スクラムコーチのウィリアム・セルヴァットら、その2年後のワールドカップNZ大会決勝で再びオールブラックスと対戦し、惜しくも1点差で敗れた世代だ。
その世代の代表選手の1人が、「あいつらも夏の遠征を経験するべきだよ」と冗談混じりに言ったことがある。
「あいつら」とは、今のフランス代表選手のこと。10か月のシーズンの疲れが溜まった身体で、24時間かけて飛行機で移動し、さらに約1か月間、厳しい試合を経験しろということだ。
◆覚悟が感じられた戦う姿勢。
ガルチエ ヘッドコーチ(以下、HC)は、今回出発前に、「この挑戦は不可能に思える。君は参加するのか?」と選手に尋ねた。参加した選手は全員「はい」と答えたのだ。
選手たちの、その覚悟が感じられる奮闘だった。
初戦は27-31。73分、28-27の1点差でリードしていたNZが、フランスの22メートル内でペナルティーを得て、タッチではなくPGを選ぶのを見て、「おおお! そこまで追い詰めているのか」と思った。
その後、フランスはボールを獲得しNZの22メートル内に入った。あそこでパスがつながっていたら!
23人中8人が初キャップ、平均で14キャップのチームがオールブラックス相手に予想以上に善戦した。
しかし、NZにとっては今季の初試合。2戦目は必ずレベルを上げてくる。絶好の金星の機会を逸した気分だったが、この経験のない、ほぼ実験に近いフランス代表は何かしてくれるかもしれないと期待を抱いた。
トップ14決勝を終えてトゥールーズとボルドーから合流した選手を含め、1戦目から10人のメンバーチェンジを行って臨んだ2戦目。前週からギアを上げてきたNZにパワー、スピード、気迫で圧倒され、戦術でも対応できず前半だけで4トライ奪われた。最終的には17-43で敗れるも、後半のスコアは14-14と食らいつき、「自分たちもオールブラックスと互角に戦えるんだ」と彼らは信じ続けた。
そして第3戦、この試合のために前週休ませたこのキープレイヤーのCTBガエル・フィクー、NO8ミカエル・ギヤール、FLアレクサンドル・フィッシャーらを再び戦列に戻し、「現状で可能な限りベストなメンバーを選んだ」(ガルチエHC)と、明らかに最終戦に照準を合わせていたことが分かった。

NZゴール前のモールからSHノラン・ルガレックがブラインドサイドをついたトライ、3本のPG、SOアントワンヌ・アストイのドロップゴールで得点し、19-17とかろうじてリードして折り返したが、後半はNZのキッキングゲームで自陣に釘付けにされた。フランスはディフェンスラインに14人が並んで黒いジャージーの進入を阻もうとした。しかし、手薄になっているその裏のスペースをNZは執拗に狙ってキックを落としてくる。今年3月のアイルランド戦ではうまく機能した戦術だが、「コミュニケーション、コントロール、そしてこのチームでの経験不足が問題だった。NZはそれを見抜いていた。見事だった」とガルチエHCが語るように集団的経験値の差が浮き彫りになった。
ラック周りの動きは改善されたが、その分スクラムで苦戦した。「フランスの選手たちは持てる力を尽くして戦ったが、それだけでは不十分だった。彼らに足りなかったのはエネルギーであり、それゆえに敵陣で攻撃を仕掛けるためのボール獲得機会も少なかった。フランス代表が得意とするFWの破壊力で縦への攻撃を展開するにもパワーと機動力が不足していた」と、元フランス代表SHのジャン=バティスト・エリサルドが「レキップ」で分析している。
この試合でのフランスのタックル数は297。選手たちの不屈のマインドセットと同時に、いかに防戦一方だったかを物語っている。勝利は手が届くようで遠かった。
◆期待に応えた新戦力。そしてフィクー。
HOペアト・モヴァカやWTBルイ・ビエル=ビアレ、FBトマ・ラモスのような選手がいれば劣勢の状態からでも突破口を切り開き得点に結びつけることもできただろう。SHアントワンヌ・デュポン、マキシム・リュキュなら、確実にキックをスタンドに蹴り込んで試合を切ってチームを救うこともできただろうという思いが頭をよぎった。
試合後の会見で「1戦目と3戦目でこれだけオールブラックスと渡り合えたのを見ると、ベストメンバーだったらどうなっていたかと思わないか?」と記者からの質問を受け、ガルチエHCは「5週間も戦い抜き、自分たちを信じ、ここで勝てる可能性を最後まで信じ続けた選手たちに対して、そのような話をするのは失礼だ。彼らは極めて勇敢で、結束していた」と選手たちの奮闘を称えた。
まさにその通り、選手たちは非の打ちどころのないマインドセットを見せたのだ。
レ・ブルーの指揮官にとって今回の遠征の狙いは「このレベルを経験したことのない選手たちの能力を引き出し、このレベルで戦い、成長できると感じてもらうこと」だった。
3連戦で14人の選手が初めて国際試合を経験し、このレベルで戦えることを証明した。中でも豊富な運動量で次々と影の仕事をこなすFLアレクサンドル・フィッシャーは3戦目の前半だけで21回のタックルを一度も外さずに成功させた。
通常は右PRでプレーすることが多いPRポール・マレーズは、イングランドXV戦も含めて全試合で左PRとして途中出場し、左PRで2戦続けて先発出場したバティスト・エルドシオ同様、ディフェンスで献身的な働きを見せた。PRの選手層を厚くしたい代表チームには好材料だ。
それぞれのクラブでの目覚ましい活躍で、代表でのプレーが期待されていたLO/FLジョシュア・ブレナン(トゥールーズ)、FLピエール・ボシャトン(ボルドー)、LOマチアス・アラガユ(トゥーロン)も期待に応えた。
初キャップ組以外でも、1年前のアルゼンチン遠征で代表デビューし、その後も11月のテストマッチ、シックスネーションズと全試合に出場しているミカエル・ギヤールがチームを率いる主戦力として活躍した。本来のポジションのLOではなく、NO8で起用されたが、ボールを持っては前進し、ディフェンスでも強烈なタックル、さらにジャッカルでボールを奪い、ガルチエHCの期待に大きく応え、満場一致でこの遠征のフランス代表のベストプレーヤーだ。
テオ・アティソグベも、スピード、空中戦、WTB/FBのどちらもこなすポリバレンスな能力を武器に、ラモス、ビエル=ビアレ、ダミアン・プノーとの代表チームのバックスリーのポジション争いに参戦する権利を獲得した。
これらの若者が、世界1、2位を争うレベルを経験し、そのレベルで戦い、勝つためには何が足りなかったのかを味わったことはポジティブな材料だ。
そして、今回多くの主力選手が休養を選んだ中で、この遠征への参加を希望し、キャプテンとして新人たちを率いたCTBガエル・フィクーの存在の大きさを書かずにはいられない。高いプレーレベル、ゲームを読む能力、そしてリーダーシップを発揮し、彼の価値をあらためて証明した。
試合後フィクーは「どんなフランス代表チームであっても、強い精神力と結束があれば、立派に挑戦に立ち向かえるということを、今回の遠征で僕は学んだ。このチームはNZのメディアや人々から、多くの批判を受け、見下されてきたが、堂々とした姿を見せられたと思っている。オールブラックスと再び対戦する時、それは借りを返す機会となるはずだ」と力強く語った。

◆やっとオフも、悩ましい現実。
次の両国の対戦に、この遠征に参加した選手のうち何人が出場することになるのかは未知数だが、1か月余りの遠征で選手間に強い絆が生まれたことはピッチ上の彼らからも伝わってきた。それを思えば、この遠征は、2027年のワールドカップに向けたチームビルディングの良い機会にもなっただろう。大会をイメージして、シミュレーションの場にもできただろう。
2018年の夏以後に代表チームに初参加したSOロマン・ンタマック、FLフランソワ・クロス、NO8グレゴリー・アルドリットらの主力選手は、南半球への遠征を経験したことがない。祖国から遠く離れた異国の地で1か月、チームメンバーだけで過ごす体験は格別だ。ガルチエHCは「南半球への遠征はロマンだ、代表選手としての醍醐味だ」とも言っていた。お互いのことをさらに知ることができる。そんなことがピッチ上の動きにも出てくるのではないか?
スケジュール上の問題で言っても詮ないことだが、今年で最後になる夏の遠征に、とうとう参加できなかった選手たちを気の毒にも思う。
来年から始まると言われているネーションズカップでも、フランスは7月に南半球で試合をすることになる。新しいシーズンのトップ14は、9月6日に開幕し、来年6月27日の決勝で幕を閉じる。今季と変わらない日程だ。ネーションズカップという形態になってもフルメンバーで戦えない状態が続くのだろうか。
遠征に参加した選手はようやくオフシーズンに入る。フランスのプロラグビー界における選手とクラブの関係、労働条件、権利義務などを定めた「プロラグビー統一規約」では、オフシーズンはクラブの公式戦終了から次のシーズンの公式戦開始までの期間と定義されている。選手には最低8週間の連続した期間が保証され、「クラブに拘束されない期間」(有給休暇と個人トレーニングを含む)と「チームでの準備期間」の二段階に分けられている。
しかし、代表チームの遠征に参加した選手には、「クラブに拘束されない期間」がさらに1週間追加される一方で、チームとの練習は最短1週間で公式戦への参加が可能とされている。これにより、代表選手は最短で6週間という短いオフシーズンでクラブの戦列に復帰することが規約上は可能だ。だが、実際の復帰のタイミングは選手のコンディションやクラブとの話し合い次第であり、夏の遠征に参加した代表選手が全員揃って開幕戦から出場することは稀なことだ。
7月24日時点で、プレーオフ進出を逃したチームはすでに新シーズンに向けたトレーニングを代表選手不在のまま再開している。来週には準決勝で敗退したトゥーロンやバイヨンヌも始動予定だが、主力選手がいない状態でシーズンの準備を進めなければならない状況は、各クラブにとって頭痛の種だ。
8月中旬には合宿や練習試合も予定されているが、代表選手はこれらにも参加できず、チーム全体の足並みが揃わないことが懸念される。
今回の遠征にも、ガルチエHCがこだわる「42人」の選手が招集されたが、クラブ側からは招集人数の削減を求める声もあがっていた。NZとの3連戦で一度も出場機会を得られなかった選手が7人いた。このことを受けて、招集人数を含め、代表選考のあり方や、選手、およびクラブの負担に関する議論が再燃することも考えられる。
【プロフィール】
福本美由紀/ふくもと・みゆき
関学大ラグビー部OBの父、実弟に慶大-神戸製鋼でPRとして活躍した正幸さん。学生時代からファッションに興味があり、働きながらフランス語を独学。リヨンに語学留学した後に、大阪のフランス総領事館、エルメスで働いた。エディー・ジョーンズ監督下ではマルク・ダルマゾ 日本代表スクラムコーチの通訳を担当。当時知り合った仏紙記者との交流や、来日したフランスチームのリエゾンを務めた際にできた縁などを通して人脈を築く。フランスリーグ各クラブについての造詣も深い。