
Keyword
9月14日。札幌パークホテル。優しい野蛮人どもがビールのグラスを指に吸いつけながら、古きよき建造物の高い天井の会場をのしのしと楽しそうに移動する。
サッポロ印の「クラシック」の瓶がテーブルに並んでいる。ラベルの色のせいなのか、なんだか白樺の林のようだ。
北海道バーバリアンズラグビーアンドスポーツクラブ50周年記念式典。
半世紀前。ベトナム戦争終結の年。6人の男が、小樽潮陵高校の校庭をよれよれと走った。「体にいいこと何かやってる?」。当時、そんな清涼飲料水の宣伝文句があった。アイドルの郷ひろみが鼻にかかった声で問いかけてきたのだ。
曲者ぞろいのはずなのに、なぜか、素直に触発されて、高校の授業でかじったラグビーを始めた。体にいいことを何もやっていなかったので、ほどなく気分が悪くなる。えずいて、その先の現象も起きた。
かくして創設時のクラブ名は「ボーミッツ」。英語(vomit)で「胃の内容物を食道を通して口腔外へ出すこと」。あの春の日曜、母校の土を汚したかすかな染みは、やがて、青々と広がる芝のグラウンドやクラブハウス、性別も国籍も年齢もさまざまな背景も超える友情、勝利の歓喜に敗北の慙愧、もちろん銘柄問わずの麦酒の壮大なる消費、うまくタレにつかった羊肉のバーベキューの匂いをこの世にもたらした。
オリジナル6。起源の6名のひとり、田尻稲雄さんこそは中核の人物である。15年前に、こうつぶやくのを聞いた。
「夢を追いかけると、よく言うでしょう。あれ、違うんだよね。夢は実現させるものなんだよね」
ビジネス書のありきたりな言い回しのようだ。しかし、北海道バーバリアンズを知る立場では、素直にうなずける。
ずっと夢にとどまった理想のクラブ環境をまさに実現させた。いまも定山渓では、メンバー有志のワールドクラスの芝管理のおかげもあり、天然のじゅうたんが、子どもの笑い声や楕円球の転がりを包んでいる。
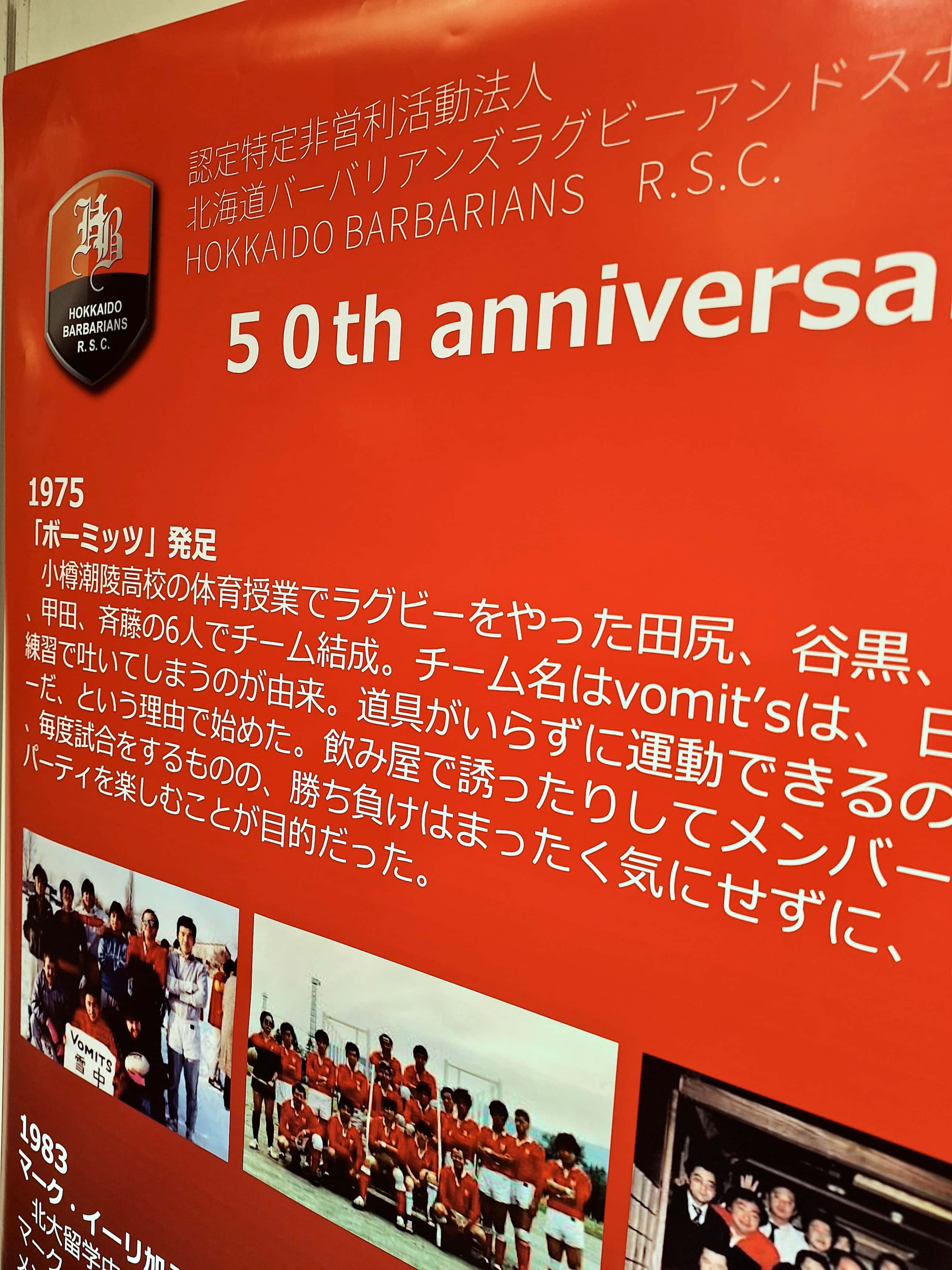
1987年。ボーミッツのままでは英語圏で対戦相手が見つからぬとの声もあって「バーバリアンズ」と改称したチームは、最初の男子ワールドカップ期間中のニュージーランドへ遠征する。そこで本場のクラブライフの一端に触れた。
見て、憧れる。それだけでなく我々もそう生きるのだと決めた。まずは生活の問題であり、さらには人生の主題へと昇華した。ここのところの、なんというのか、思考の跳躍力が後年の「夢=実現」につながっていく。
翌88年に理想追求のための議論を始め、ニュージーランドの同志との交流を深めた。1999年。NPO(非営利活動法人)に認証される。
2004年6月13日。ジュニア、シニアのA、B、C、U19合同というバーバリアンズのそのころの全カテゴリーが同日の試合に臨んだ。「ゆりかごから墓場まで」の具現の一歩である。
そして忘れがたき2007年。定山渓のNTT東日本の休眠化したグラウンドや設備の購入に踏み切る。かつて「草ラグビー」と呼ばれた集団は、とうとう草ならぬ芝の上を駆ける宿望を遂げた。3年後には女子チームを結成。2025年現在、バドミントンやアイスホッケーの活動も充実、総合スポーツクラブへウイングを伸ばしつつある。
と、バーバーこと北海道バーバリアンズのヒストリーをおおまたでなぞった。本コラムにとって大切なのは、そこにいる人間の言葉である。
メディカルシステムネットワーク代表取締役社長でもある田尻稲雄さんの次の一言もよく覚えている。北海道バーバリアンズ方式とは。
「自分よりできる人間をどんどん巻き込む」
これ、ラグビーのクラブにとって、いわば長生きのために欠かせぬ文化である。そうであるのに、なかなか実行されない。
たとえば、あるチームに監督やコーチがいて、部員のために「自分よりできる人間」をどんどん巻き込むか。案外、できない。彼がきたら、彼女がきたら、わたしよりも選手の心をつかんでしまう。みんな、そっちを向いちゃう。なんておそれるのだ。競技を問わず、そんな例ならあまた目にしてきた。
学校という閉じたクラブの例ではあるが、古くからすたれぬところ、一例で国内ラグビーのルーツ校の慶應義塾大学には、後輩、後進のために「自分よりできる人間をどんどん巻き込む」伝統というかカルチャーは厳然と生きている。生きているはずだ。
早稲田大学も、昔にコーチをしていたので、よくわかるが、その年度の4年部員の幸福だけを、いくつになっても指導陣は考える。だから卒業生のだれがスクラムの格別なノウハウを有しているのか、4軍の若者のハートに火をともすのはどいつか、などなど常に情報を集めては招いた。四半世紀前の事実だが、ずっと変わらぬと信じられる。
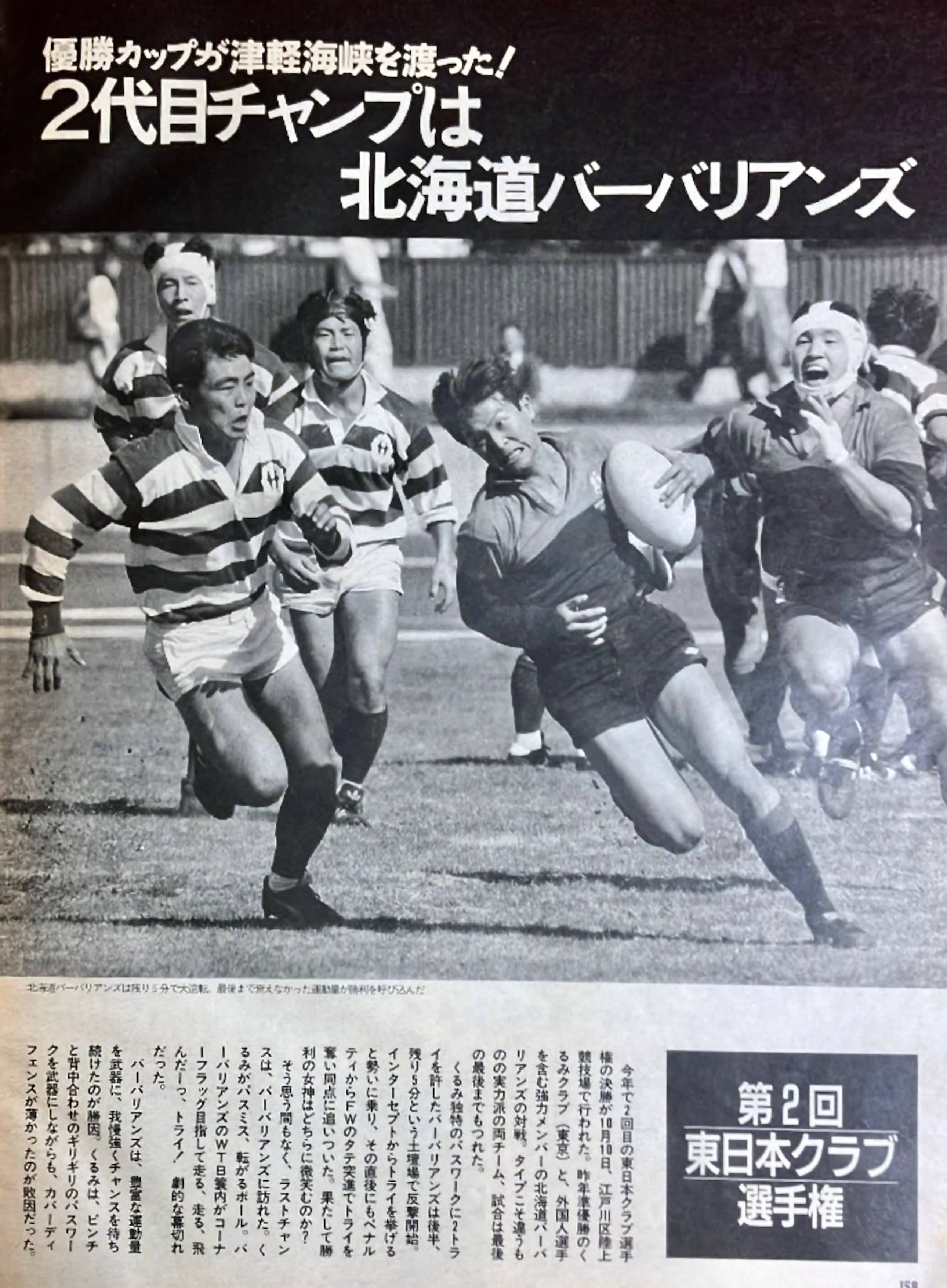
北海道バーバリアンズは構成員のだれよりも大きい。であれば「巻き込みたくなる」ほうが自然な感情だ。反対から述べると、リーグワンであれ、大学であれ、いかなる名将も、いかなる出資者も、いかなる名選手も、クラブよりは小さい。これぞ神髄なのだ。
バーバリアンズのオリジナル6である谷黒正明さんの14年前の発言も忘れがたい。
「結局、みんな自分のことより他人のことを考えるような優しい人間なんですよ」
仲間を語っている。優しいバーバリアンは優しいから高い壁を越えられた。
日本代表キャップ98 の大野均さんは10年前のインタビューで静かに述べた。
「だれかのために力を尽くす。自分のためだけでは妥協してしまうから」
ラグビーの本来は「利他」なのである。道徳の領域でなく、そうしたほうが試合にも勝てる。
バーバリアンズの50周年式典。女子7人制のディアナの吉田鳳子、男子Aチームの濱口竜輝の両キャプテンが壇上で挨拶をした。ともに、感謝にとどまらず、ここでラグビーを続けることの使命をスピーチににじませた。開かれたクラブの存在理由をふたりが体現していた。
順不同、無作為ならぬ作為抽出で、千里馬クラブにも、宇都宮VOLT’Sにも、日本製鐵九州大分リサイクロンズにも、マンダラ東京RFCにも、弘前サクラオーバルズにも、神奈川タマリバクラブにも、くるみクラブにも、やんばるラグビークラブにも利他という大義がある。その先に「ひとりも孤独にしない共同体」の可能性は待つ。そこが、それこそが日本列島のラグビー無形文化財である。
本コラム筆者は北海道バーバリアンズの式典で話をさせてもらった。旧知の善き人との再会に心が弾むばかりで、最後に言うつもりの一節をうっかり忘れた。それは以下のくだり。
「いつか、定山渓のグラウンドを奪いにくるものがあるなら、戦争であれ、戦争に優しい為政者であれ、自由を奪う体制であれ、そいつはここにいる私たちの敵だ」
本心です。
さて、おしまいに。かのリーチ マイケルの祝辞が映像で流れた。スクープ! 札幌の育んだ英雄はそこで約束している。
「僕の日本のラグビー人生の始まりは北海道、そして僕のラグビー人生、選手としての終わりは北海道バーバリアンズにしたいなと思います。北海道のジャージーを着て全国制覇をめざして頑張りたいと思います」
本人はいないのにいるみたいな拍手が鳴った。


